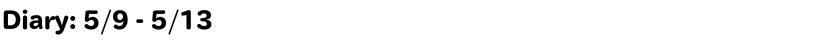
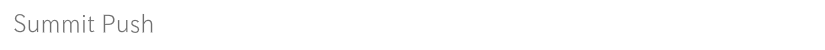
 Everest summit
Everest summit
Everestキャンプの標高
EBC 5,200m
C1 6,000m
C2 6,400m
C3(High camp) 7,400m
C4 7,900m
Summit 8,848m
5/9 @EBC
 Crevasse of Western CWM
Crevasse of Western CWM
(5/8) 23:30 起床。天気がいい割には、暖かい夜だ。風は殆どない。
朝食は軽く食べる。珍しく、スクランブルエッグが出た。
今まで、卵料理は、目玉焼きかオムレツのどちらかを作っていたのだが、今朝は、グレッグのリクエストで、スクランブルエッグになったのだ。目先が変わって良い。無敵モードの恩恵だ。
ちょっと和む。
今日もいい天気だ。エベレストの北陵は風が強いらしいが、我々の側は問題ない。
 Ladder climbing
Ladder climbing
00:30 出発。プジャの祭壇に手を合わせて、キャンプを出ていく。体調はいい。楽に歩けそうだ。
少しゆっくり目のペースで歩いていく。一度、歩いていたので、地形がよくわかって歩きやすい。
フットボールフィールドを歩いていた時に、グレッグのヘッドランプが消えた。電池切れだ。彼は替え電池を忘れたので、その場でリッチーに電池をもらい、そのまま替えてもらった。毎度のことだが、皆、おいおいといった表情だ。
ヤコは少しナーバスになっている。ロープの結び目でカラビナをかけ替える時に手間取り、いらいらしている。寝不足だからか?
ポップコーンフィールドに入ると、リッチーから、先に行ったらと言われた。私が力が余っているのが分かったのだろう。先に登り始めた。2~3分後には、皆が見えなくなった。
👟 👟 👟
04:45 快調に登ってIcefallの上に着く。そのまま30分ほど待った。ドクターのトレイシーは到着したが、他のメンバーは来ないので、C2へ出発する。
知り合いのシェルパ達が下ってくるのとすれ違う。ニマ、ウルケン、フラ達だ。
C1からC2の間は、風はなかったが寒い。早い時間だからか。
やっぱり、C2は、近くに見えて遠い。なかなか着かない。
 C2 in the snowing
C2 in the snowing
08:30 C2に到着。止まると寒い。早速、ダウンスーツに着替えて、皆を待つ。
トレイシーの後には、グレッグが到着した。彼はお爺さんだけど、野生の本能で生きていて元気だ。
今日は寝て暮らす。これから、降りるまでは、ヤコと同じテントだ。
20:00 消灯。雪が降っている。
5/10 @C2
 Richie @C2 dining
Richie @C2 dining
08:00 昨晩の雪もあがり、天気が良くなった。
テントの中は、湿気の露でいっぱいになり、雨のように滴たってきた。耐えられず起きる。
ディスカバリーの撮影隊のジョーは、ダイニングテントに寝ていた。同テントのグレッグのいびきに耐えられなかったらしい。
今日は、天日干しをして明日の支度だ。
ディスカバリーチャネルは我々の登頂の記録と共に、レスキューの状況を撮影している。
今日もC3から、レスキューの依頼が出ていた。人が多いので、きりがない。撮影のチャンスも多い。ディスカバリーは目の付け所がいいのかな。
20:05 消灯。71%/73bpm。まあまあかな。0時前位までKindleを読む。
5/11 @C2
 Lotseface - lower part
Lotseface - lower part
05:15 起床。
06:30 出発。
雪明けの天気。ローツェフェイスの下に小さな雪崩が起きた。手前で少し待って、安全を確認する。
今日は荷物が重い。そして、少しゆっくり歩きすぎ。暑い。
前回より雪がついて、今回の斜面は少し歩きやすい。しかし、息が切れる。
 C3 - photo by Jaco
C3 - photo by Jaco
午後から、雪が降ってきた。C3に到着。
今日は、遠征中、最高に疲れた日だ。
19:00 消灯。
5/12 @C3
 Route to Yellow band
Route to Yellow band
5時ごろから、起きたり寝たりを繰り返している。
朝飯は味噌汁とチョコ。なんか、これが落ち着くのだ。
09:30 出発。日の光を浴びたローツェフェイスが美しい。 Yellow band
Yellow band
イエローバンドの下まで、斜行してトラバース気味に登っていく。
イエローバンドは、古代の地層からできた岩盤帯だ。黄色と言うより、クリーム色だが。
岩の基部につくと、そこから弱点をついて登る。岩と雪のミックスクライミングで、15mくらいの壁を乗り越すのだ。
 Straight up
Straight up
多少、力技も含めて壁を乗り切ると、そこからは、長い直登でローツェ山頂への分岐まで登る。この時間は、日に照らされて、いよいよ暑くなってくる。
 Looking down Lotseface
Looking down Lotseface
遠くに、ジェネバ・スパーが見える。サウスコルから伸びている稜線だ。この稜線に向かって、大トラバースのルートが続いている。長い長いルートが、大きくコの字型を描いて、稜線直下まで続いている。
そこからは、稜線上まで急登のルートだ。60度くらいの傾斜だろうか。凍っている上に、すれ違うのが難しいくらい狭い。
先に歩いている人は少ない。7-8人くらいか。先を見ると、ジェネバ・スパーのところで、スローな登山者がいるらしい。人があまりいないのに、詰まっている。そこまで快調に歩いて行った。
ジェネバスパーにつくと、再度、詰まっていた。また、スローな登山者が出たらしい。しかし5分くらいで、普通のペースになる。
稜線から、サウスコルまでは、再びトラバースルートだ。30分くらいの歩きで、C4に着く。
 Everest from C4 - photo by Tracy
Everest from C4 - photo by Tracy
トラバースルートに入ると直ぐに、スローな男女登山者に会った。日本メーカーのザックなので、日本人だろうか。古い山男っぽい雰囲気だ。ただ、狭い道なのに大変遅い。そして、道を譲らないくらい集中している、困ったちゃんなのだが...
なんとか、抜かさせてもらった。
15:00 C4に着く。お茶を飲む。落ち着いた。
ここは、デスゾーンです。何気につぶやくジョークも死んでいる。
 C4 photo by Jaco
C4 photo by Jaco
夕食はカレーヌードルにした。
軽くで十分。
18:40 消灯
5/13 @C4(7,900m)
 Lotse from Everest summit
Lotse from Everest summit
00:05 起床。同じテントのヤコが起きないので起こす。
また、みそ汁の朝食。ベスパとチョコも。
01:15 出発。-5℃くらいか。風もなく、暖かい。
最初に、サウスコルの氷の雪原を横切る。1994年の大量遭難で皆がさまよった場所だ。なだらかに傾いた雪原は、リング・ワンダリングが起きやすい。視界が悪いと、ぐるぐる、いつまでも、回ってしまうのだ。日本だと、八甲田山とか、千畳敷の浄土乗越とかの地形だ。
そして急登が始まる。60度くらいか。少し雪がついているので、歩きやすい。
長い登りだ。星がまたたく。あまりに暗くて、山影と空の境目はわからない。
上のほうに、少しヘッドライトが見える。昨晩のうちに出発した隊だ。でも、なかなか進んでないようだ。だんだん近づいてくる。
酸素マスクが、うまくあってないようだ。外気が入ってこない時がある。苦しくなり、途中でマスクをずらして、息をする。それって酸素マスクの意味がある?
俺は、今日はソナムというシェルパと組んで歩いている。彼とは昨年のK2でも一緒だった。
あまり疲れないように歩いた。今日は、長丁場だ。しかし、ソナムは、シェルパペースで歩こうと言う。先頭に追い付くと、ペースが落ち着いた。
👟 👟 👟
バルコニーについた。8,400mの標高、頂上までの間のチェックポイント1と言ったところか。我々の先を歩いていたアジアントレッキングの隊は、ここでばてて、休んでいた。
2-3分休んで、また歩き始める。
 Photo by Greg
Photo by Greg
バルコニーから南陵までは、更に急な傾斜になっている。雪がついていなければ、つらい登りだっただろう。
途中、今度はジャケットグローブの隊がいた。彼らのヘッドランプは、これまで見えなかった。一体、何時に出発したのだ。
彼らに追いつき、そしてロープから外れて、追い越す。エンジン全開で、彼らの横を登るのだ。ここはつらい処だが、いつまでも彼らの後ろでトロトロはしていられない。
4時過ぎから、雪が降ってきた。風も強くなる。10m/sくらい。時々20m/sになる。厳しい天気となった。
マスクも更に調子が悪い。息の湿気が凍ってきた。
マスクをずらすと、息がゴーグルにもかかり、凍り付く。視界がぼんやりとしている。やがて、真っ白になってきた。ゴーグルを拭いても、何も変わらない。強風でゴーグルを外すわけにもいかない。
吹雪が強くなってきた。顔に吹き付けてくる。頬は凍傷気味だ。しかし息が苦しいので、バフで顔を覆うわけにもいかない。いやいやいや、大丈夫か?
南陵の手前で、アンドレアスが遅れる。かなり疲れているようだ。彼も、大丈夫か。
👟 👟 👟
 South peak
South peak
南陵の頂上で、一旦休む。そこからまた歩くが、ルートが狭くなってきた。
ラッセルから無線が入る。EBCから見えているらしい。予想よりも悪い天気だったが、なんとか行けそうだと答える。
ルートの脇に、足を踏み外す。落ちかける。目が見えないので、しょうがないが、そこからのリカバリーも大変だ。やばいやばいやばい。
再度、足を踏み外した。危ない。そして、めちゃめちゃ、疲れる。
もう一度、ここで止まってリカバリーをする。荷物を下ろし、ゴーグルを洗う。マスクについた氷を溶かし、強く顔に押し付ける設定にする。
 Hilary step - photo by Tracy
Hilary step - photo by Tracy
やっと息ができる。そして目が見える。
俺、復活!って感じだ。
そうなると、ヒラリーステップは、楽勝だった。丹沢の尾根を歩いているようだ。
そして、頂上が目に入る。やっと盛り上がってきた。5分後には、あそこだ!
風も雪も収まってきたようだ。
 Summit view
Summit view
頂上は、シンプルなチョルテンの旗が飾ってあった。ラマ教の経典もおいてある。
そして、遥か彼方まで、チベット高原が広がっている。
ここからの景色は雄大だ。
👟 👟 👟
 Sonam and I
Sonam and I
写真をとる。自分と、ソナムと。他のシェルパもやってきた。
30分くらいゆっくりしてから、降り始める。
だんだん、空も晴れてきた。 Hilary step - photo by RIchie
Hilary step - photo by RIchie
ヒラリーステップで、上ってきたジャッケド・グローブの隊とすれ違う。かなり消耗しているようだった。 Lotse from Everest
Lotse from Everest
向かいの山は、ローツェだ。頂上へのクーロワールがよく見える。天空に続く岩溝だ。
南陵までもどると、ドクターのトレイシーが倒れこんで動けなくなった。ずっと無理をしてきたらしい。ここは、ヘリを呼べる高さを越えている。だましだまし降りるしかない。
シェルパが彼女の荷物を運ぶことにした。それでも、彼女は、なんとかその日うちにC2まで降りることが出来た。
 Steep slope
Steep slope
南陵から下の急坂はアームラップで降りる。大下りのルートだ。足にくる。
そしてまた、バルコニーで休む。飲み物で生きた心地がした。
そこには、途中で登るのを諦めたらしい、アジアントレッキングのメンバーがいた。
昨年、色々とやらかした問題児だったジョエルだ。まさか此処で会うとは。そして、去年は自信たっぷりだった彼が登れなかったとは。
彼らを抜かしてC4まで下りると、テントで昼寝をした。そしてまた下る。
ジェネバスパーの狭い急坂では、人がゆっくり上ってくる。微妙に途切れない列で、いつまでも降りられない。
稜線上で降りるタイミングを待っていたら、20分近く経ってしまった。
行動食も食べているが、エネルギーはとっくに切れている。
喉ももからからだ。
そして暑い、一人旅だ。
👟 👟 👟
イエローバンドの下りでは、8環を使って、懸垂下降をした。今回の遠征では初めてだな。
C3のあたりで、雪に赤い点々が見える。光の反射で赤い虫が雪の中で光っているように見える。しかし写真をとると赤くない。謎だ。
少し座って休む。エベレストに登った実感が沸いてくる。
しかし、長い。南陵から延々とアームラップを続けている。足もがたがただ。
 Izuishi glove
Izuishi glove
今回、新兵器として、日本の手袋の専門家に、オーダーメイドで手袋を作ってもらった。暖かく使いやすい。そして、高い耐久性で、ここまでのアームラップをこなしている。いいぞ!
 Break time @the bottom of LF
Break time @the bottom of LF
ローツェフェイスを降りきって、C2の手前で、再度大休止をした。もう水が無かったので、きれいそうな雪を集めて食べる。冷たくて気持ちいい。
雪を食べると、結局、土や空気の細菌を取り入れてしまうので、腸内細菌バランスが変わり、下痢気味になるのだが、しょうがない。もう頂上に登ったので強気だ。
さんざん休んで、日が傾き、寒くなってきた。C2へ戻る。
アンドレアスは、咳が止まらなくなっただけでなく、指が凍傷にかかった。小指は二倍くらいまで腫れ上がっている。しかし黒くなっていないので、まだ大丈夫なはずだ。
いろいろあったが、皆、頂上まで登れてよかった。
